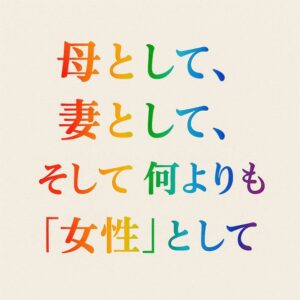発達障害は存在しない(発達障害とは大人の基準で作られたもの)
発達障害は、単に学習が遅いこととは異なる概念です。
いくら情報が入ってきても脳がそれを処理できなければ「遅い」とされてしまいます。
認識にもさまざまな種類があります。
文字を認識するのが苦手な子どもでも、映画やアニメはよく理解できることがあります。
つまり、子どもがどのようなものを認識しやすく、どのようなものを認識しにくいかを観察すれば、文字の認識が苦手でも、映画や音声を素早く処理できる子どももいるということです。
認識は、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚という5つの感覚器官を通じて行われます。
5つの感覚のうち一つに問題があると、他の感覚が必ず発達するようになります。
したがって、どれが良くてどれが悪いということは言えません。
もし聴覚に問題がある場合、視覚や触覚などが非常に敏感に発達することがあります。この「敏感さ」は良い場合もありますが、悪い刺激を受けると大きなストレスになってしまうことがあります。たとえば、食べ物がまずいとき、味覚が発達していなければ「まずいな」で終わりますが、味覚が敏感な子どもは、その瞬間に強いストレスを感じることがあります。
その特定の発達した感覚を活かし、不足している部分にどう繋げて補っていくかを考えることが、治療法を探すということです。しかし、常に何か問題があると言い続けると、逆に問題を作り出してしまいます。
子どもを簡単に評価してはいけません。
発達が少し遅いからといって、すぐに発達障害と判断してはいけません。
もちろん、脳や身体の検査で明確な問題がある場合は別です。
先天的に見えない、聞こえない、あるいは後天的に見えない、聞こえない場合でも、他の部分が発達します。
聴覚障害のあるピアニストのリズムは非常に美しく、聞こえないのにピアノを弾けるのは、触覚や他の感覚が発達しているからです。
ウーファースピーカーを使えば、音楽は体で感じられます。
聴覚障害のある子どもたちは、耳で音楽を聴くのではなく、体で感じ取ることができます。
言葉のどもりは、チック障害の一つで、強迫性の傾向と結びついていることがあります。
しかし、「話す」というのは表現であり、その表現の仕方は発達障害とは関係ありません。
発達障害とは、認識された情報が脳でうまく処理できないときに現れる現象です。
他の感覚が発達していれば、それを基にして不足している部分を少しずつ補っていけば、問題は自然に解消されます。つまり、発達している部分とそうではない部分とのバランスをどう取るかを見つけることが重要です。
私たちが今、発達障害と断定して治療しようとするのは、子どもの今の状態を問題視しているからです。しかし治療を始めてしまうことで、かえって本当に障害となってしまう場合もあります。
子どもを大人の観点で見てはいけません。
子どもは生まれてから関係適応期を経て、自我形成期に入っていきます。その途中で何か問題があると大人が判断するのは、あくまで大人側の観点です。その子が将来どんな人になるかは、誰にも分かりません。
子どもを障害と決めつけ、原因も分からないまま治療を始めてしまうと、治療もうまくいかず、その子の長所まで失われてしまう恐れがあります。